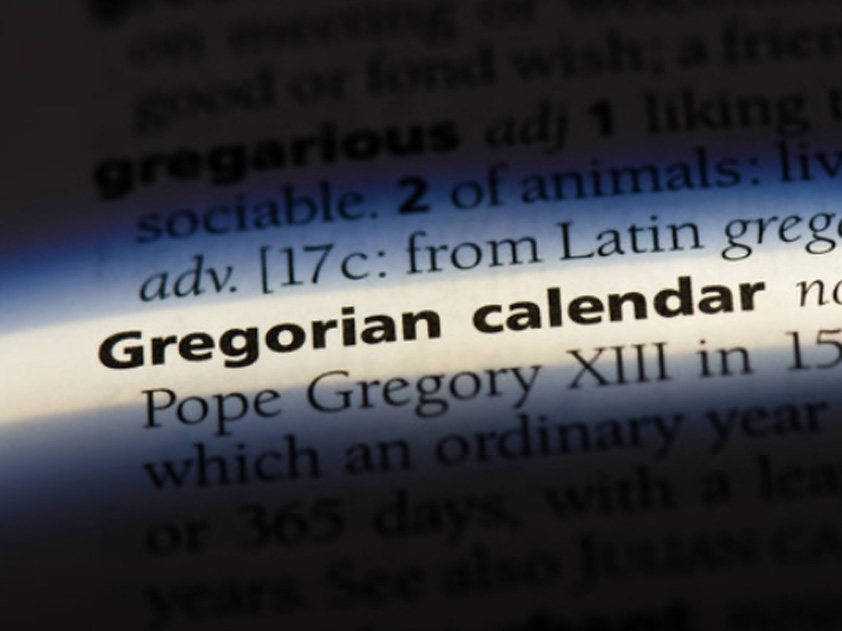昨日の稿では、数え年と太陰太陽暦が、単なる年齢計算や暦法ではなく、生命の始まりをどう捉えるかという根源的な生命観と結びついていたことを述べました。
今日は、その前提となる「暦」そのものについて、もう一歩踏み込んで考えてみたいと思います。
明治5年、政府は太陰太陽暦を廃し、太陽暦(グレゴリオ暦)を採用しました。
この改暦は、欧米諸国との外交や貿易の便宜を理由に行われましたが、その実施は極めて拙速でした。
旧暦の明治5年12月3日を、わずか23日前に告知したうえで、新暦の明治6年1月1日とするという、前例のない改暦だったのです。
この時期に改暦が行われた背景には、当時の政府の深刻な財政難がありました。
旧暦では、翌年の明治6年は閏6月を含む13か月の年でした。
そのままでは官吏の俸給を13か月分支払わなければならない。
そこで、12月を2日間で打ち切り、新暦に移行することで、結果的に2か月分の俸給を節約できる――そのような計算が働いていたことは、今では広く知られています。
仮に、太陽暦への移行そのものが時代の趨勢であり、避けがたいものであったとしても、ここで問われるべきなのは、「どのような暦に切り替えたのか」「何を犠牲にしたのか」という点です。
旧暦において、正月は春の始まりでした。
だからこそ、新年の挨拶は「初春」「迎春」「新春」であり、これらは短歌や俳句の季語として、生活の感覚と密着していました。
ところが、新暦では元旦は真冬に位置し、立春は2月初旬です。
暦の上では一年が冬から始まり、冬で終わるという、季節感としては極めて不自然な構造になっています。
その結果、冬の最中に「初春」と言い、春の気配を実感できないまま季語だけが先行する――言葉と実感の乖離が生まれました。
この「ずれ」は、単なる風情の問題ではありません。
自然の移ろいと人の感覚を結びつけてきた言霊や数霊が、制度変更によって曇らされていった過程そのものだといえます。
農事暦や海洋暦として機能してきた旧暦では、春夏秋冬がそのまま一年の循環を形づくっていました。
八十八夜や二百十日といった生活に密着した指標も、立春を起点に数えられています。
そう考えれば、仮に太陽暦を用い続けるとしても、元旦を立春に合わせるという発想は、決して荒唐無稽なものではありません。
実際、戦前には「真正太陽暦」と呼ばれる構想がありました。
伊勢の皇太神宮上空を通る子午線を基準とし、立春を元旦とする日本独自の太陽暦を国際的に提案することが、国際連盟の場で検討されていたのです。
しかし、我が国が昭和8年に国際連盟を脱退したことにより、この構想は実現しませんでした。
太陰太陽暦には確かに不便な点もありました。
しかし、それは致命的な欠陥ではなく、実生活においては多くの利点と知恵を備えていました。
新暦を直ちに廃止せよ、というつもりはありません。
ですが、少なくとも文化と伝統を守る観点から、新暦と旧暦の併記併用を公式に認めるという選択肢は、真剣に検討されるべきではないでしょうか。
実際、近隣国である韓国では、そのような運用が行われています。
暦の改変は、時間の数え方を変えただけではなく、自然との関係性、季節の感じ方、そして生命の捉え方にまで、静かに、しかし確実に影響を及ぼしてきました。
制度は時代とともに変わります。
しかし、自然とともに生きてきた先人たちの時間感覚や季節感まで切り捨ててしまってよいのかどうか。
その問いを立てること自体が、いま私たちに求められているのではないでしょうか。