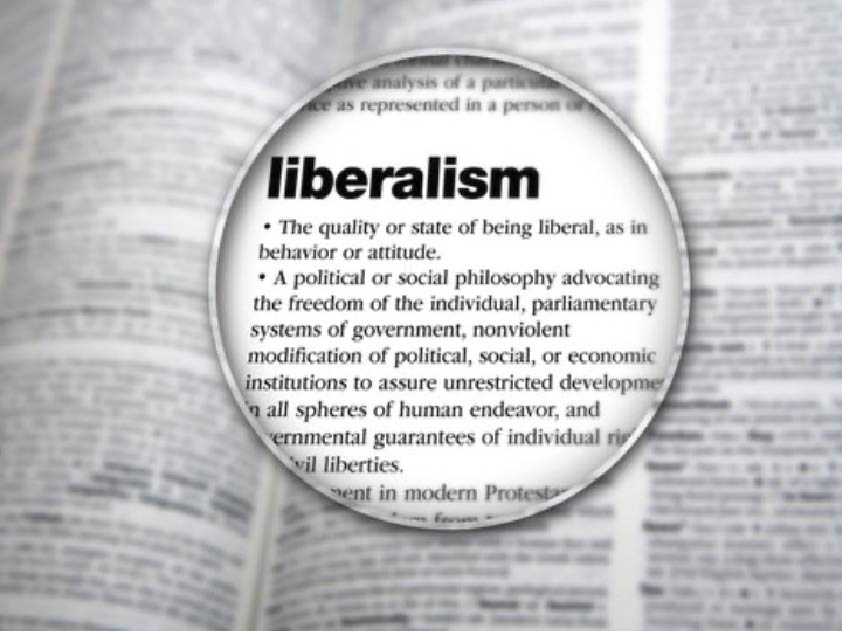川崎市は『子どもの権利に関する条例』なる恥ずかしき理念条例を平成12年12月に全国の自治体に先駆けて制定させました。
ここで言う「子どもの権利」とは、子どもにはありのままの自分でいる権利があるとか、宿題をやらないくていい権利があるとか、子どもには生まれながらにして権利と自由と尊厳が備わっているという類の権利です。
ちなみに、条例案が川崎市議会に提出され、全会一致で可決成立したのは私が川崎市議会議員になる以前の話です。
理念条例は、その存在事態が有害である場合がほとんどで、子どもの権利条例のほか、自治基本条例、議会基本条例なども典型例です。
子どもの権利条例の法的根拠は、平成12年5月に国連で採択された『児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書』にあります。
その名のとおり議定書の主眼は、いわゆる開発途上国などで問題となっている児童売買や児童売春などの撲滅にあるわけですが、これを国際的にも豊かで安全なわが国の教育現場に持ち込むと「子どもたちがありのままの自分でいる権利」に変貌するわけです。
そもそも議員にしても市長にしても役人にしても、「権利」という言葉が持つ真の意味を理解されていない人たちが多すぎます。
ご存知のとおり「権利」は英語で「Right」です。
明治初期、英語の「Right」という言葉が輸入された際、この和訳をどうするかということが検討されました。
本来、「Right」には右とか、正義とか、直線とか、保守とかの意味があり、根源的には人が国家による不当な制約を拒絶することができる立場を表します。
この複雑な言葉の和訳について、のちに最後の将軍となる徳川慶喜の家庭教師をも務めた津和野藩士の西周(にし あまね)は「権利」と訳し、かの福澤諭吉は「通義」と訳しました。
西周の言う「権利」は「利益を権力に対して要求する地位や資格」という意味であるのに対し、福沢諭吉の言う「通義」は「正義、道理に通じてこれに適った地位と資格」という意味になります。
さらに福沢諭吉は「もしも“権利”がRightの訳語になれば、後世において必ず混乱と禍をもたらす」と予言していました。
こうした議論の結果、「Right」の訳語は西周が提唱した「権利」に決まってしまいました。
しかしながら福沢諭吉の予言は的中し、昨今の日本社会では「権利」の御用による混乱と弊害が生じています。
今や「権利」という言葉は混乱と弊害を通り越して、その字が並び替えられ「利権」と同義語になっていると言っていい。
つまり、利権を追及すること、個人主義を徹底することが権利の本質になってしまったのです。
もしも福沢の言う「通義」であったなら、その正義や道理の中には「家族の尊厳」も含まれていたことでしょうが、「権利」だとまさに利権なので家族は完全に排除されてしまいます。
福沢諭吉が西洋かぶれであったことは知られていますが、そんな福沢諭吉でも「通義」には、むき出しの個人ではなく家族や社会の中で関係性をもつ個人を感じていたのだと思われます。
言うまでもなく個人主義と、それを善とするリベラリズムこそ諸悪の根源です。
占領憲法は第13条で個人主義を謳歌し、基本的人権が不可侵の永久の権利であると第87条でも宣言しています。
そして第24条では、「家族」に関する事項は個人の尊厳を否定するものとして片隅に追いやられ、全く歓迎されないものとして扱われています。
すなわち、家族よりも個人が絶対的に守られる「個人主義」により、家族主義は完全に否定されてしまったわけです。
実は戦前においてもそうした傾向があったということで、文部省は『国体の本義』を作って「個人主義」を批判したものの、それは充分に徹底されずに敗戦を迎え、占領憲法の制定に至り、権利が利権に、個人主義が利己主義と同じになってしまったのです。
占領憲法を全否定しなければならない理由は、この点にもあるわけです。
それにつけても、「Right」を「権利」と訳さず、福沢諭吉の言うとおり「通議」と訳していたならどうなっていたか。