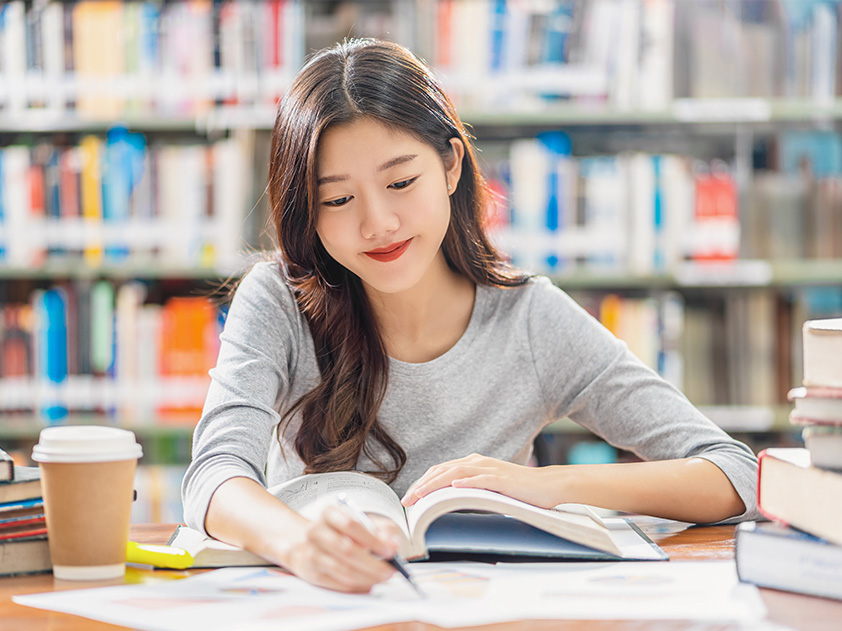国立国会図書館では、2021年度から2025年度までを「デジタルシフト推進期間」と位置づけ、所蔵資料のデジタル化を急速に進めてきました。
その数は2025年度末までに約480万点に達する見込みであり、これは2000年までに刊行された国内出版物の大半がデジタル化される規模で日本の知識基盤がいままさに大きな転換点を迎えていることを物語っています。
この変化を、私たちは単なる技術革新として受け止めてよいのでしょうか。
それとも、図書館という公共施設の本質的な意味が変わりつつあると見るべきでしょうか。
以下、いくつかの観点から考えてみます。
デジタル化の最大の功績は、物理的な制約を超えて、誰もが知識にアクセスできるようになったことです。
これまでは、東京・永田町の国立国会図書館に出向かなければ読むことができなかった貴重な資料が、地方の図書館や自宅からでも閲覧できるようになりました。
特に、障碍のある方、子育てや介護で外出が難しい方、遠隔地に住む研究者や学生にとって、この変化は「知識の公共インフラ化」とも呼べるものです。
すなわち、図書館は地理的な格差を是正する装置へと進化しつつあります。
もう一つの意義は、書物という文化遺産を次世代へと伝えるための保存手段にあることです。
紙の資料は時間の経過とともに劣化し、災害や火災によって失われるリスクもあります。
デジタル化は、そのような資料を劣化から守り、複数のバックアップによって半永久的に保全することを可能にしました。
つまり、デジタル化とは単なる利便化ではなく、「文化のアーカイブ化」――すなわち知の永続化という使命の延長線上にあるのです。
しかし、デジタル読書には限界もあります。
紙の本を読む行為には、ページをめくる感覚、紙の質感、書き込みの痕跡といった身体的な体験が伴います。
これらの動作は、脳内で情報を長期記憶へと定着させる重要な手がかりになります。
一方、デジタル画面上で読む場合、脳は「情報を保持する」よりも「必要なときに検索する」モードで働きやすくなると言われています。
結果として、知識が血肉化しにくくなり、発想の跳躍や創造的思考が生まれにくくなる傾向があるのです。
とはいえ、デジタル化は図書館の終焉ではなく、むしろ進化の第一段階だといえます。
これからの図書館は、単に「本を読む場所」ではなく、読書会、調査相談、資料展示、アーカイブ教育などを通じて、知識を共有し、対話し、創造する空間へと役割を変えていくことでしょう。
つまり、アクセスはデジタルで、思索はアナログで。
図書館の本質は、情報の倉庫ではなく、人間の知を深めるための「場」にこそあるのです。
デジタルの波が押し寄せる今こそ、図書館は「人が知と出会い、思索する場」としての本質を再確認すべきときではないでしょうか。
デジタル化の恩恵を享受しつつも、人間の思考と記憶を支えるアナログな読書の価値を見失わないこと――それこそが、これからの時代における“知の公共”のあり方だと思います。