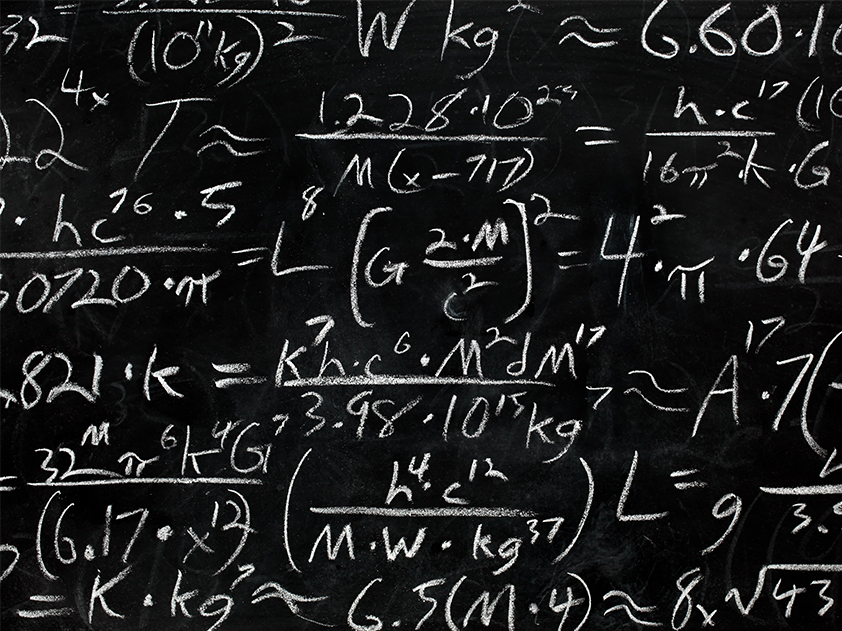主流派経済学は、単なる学問の領域にとどまらず、政策決定や社会のあり方に大きな影響を及ぼしてきました。
その経済モデルはGDPの見通しや自由貿易協定の効果を試算する際に用いられ、政策の「科学的根拠」とされて政治判断を左右しています。
審議会や政府の諮問機関では、都合のよい理論が都合よく引用され、メディアを通じて「財政は破綻する」などの発言が繰り返し流布されてきました。
ここでは内容よりも、発言者が東大教授や有名学者といった「権威」であることが重視される傾向も否めません。
主流派経済学の根底には「方法論的個人主義」と呼ばれる学問的立場があります。
これは、社会現象のすべてを「個人の行動」に還元して説明しようとする方法であり、思想としての個人主義とは区別されます。
この立場では、人間は孤立した「原子論的個人」として仮定され、制度や文化といった複雑な要素は切り捨てられます。
補足すると、学問においては「存在論」と「方法論」は表裏一体です。
存在論とは「何を対象とするか」「世界をどう切り取るか」という前提のことであり、方法論とは「その前提に基づいてどう分析するか」という道具立てです。
主流派経済学は「人間は合理的個人である」と存在論的に仮定するがゆえに、その方法論は必然的に「数理モデルによる個人の最適化分析」となります。
逆に「人間は制度や文化に埋め込まれた存在だ」と仮定するならば、方法論は歴史分析や制度研究へと変わります。
では、なぜ主流派経済学は「方法論的個人主義」を採用したのでしょうか。
それは、経済学を「自然科学のように見せたい」という衝動があったからです。
物理学のニュートン力学を模倣し、数式によって社会を説明できる学問にしたいという願望が、個人を計算可能な単位に切り縮めてしまったのです。
こうして合理的経済人という仮想の主体が生み出されました。
例えば、消費者は効用を最大化し、企業は利潤を最大化すると仮定されます。
そこには「予算制約式や生産関数を用いれば、ラグランジュ乗数法で最適解が導ける」という前提があり、さらにワルラスやアロー=ドブリュー・モデル(一般均衡モデルを数式化したモデル)によって、こうした個人の最適化行動を積み重ねることで、市場全体の「一般均衡」を数学的に証明したことになっています。
後に発展したDSGEモデル(中央銀行等が採用しているシミュレーションモデル)も、基本的には同じ土台の上にあります。
しかし、ここには決定的な欠陥があります。
この方法論では、貨幣、制度、歴史、文化といった要素はモデルから排除されてしまいます。
貨幣は人と人との「債権・債務」の関係から生まれるにもかかわらず、数式に載せられないために無視されてきました。
結果として、現実経済の根本を捉えられず、たびたび予測を外しても理論を修正しないという頑なさにつながっています。
結局のところ、科学的に見えること、つまり「科学っぽさ」を優先するあまり、現実を歪めてしまったのが主流派経済学だといえるのです。
学問は本来、現実を理解するための道具であるはずです。
しかし、現実を切り捨ててでもモデルを守ろうとする姿勢は、もはや科学の本義から外れているといわざるを得ません。
健全な社会を築くためには、この「科学っぽさ」に惑わされず、制度や関係性を踏まえた現実的な経済理解を取り戻さねばならない。