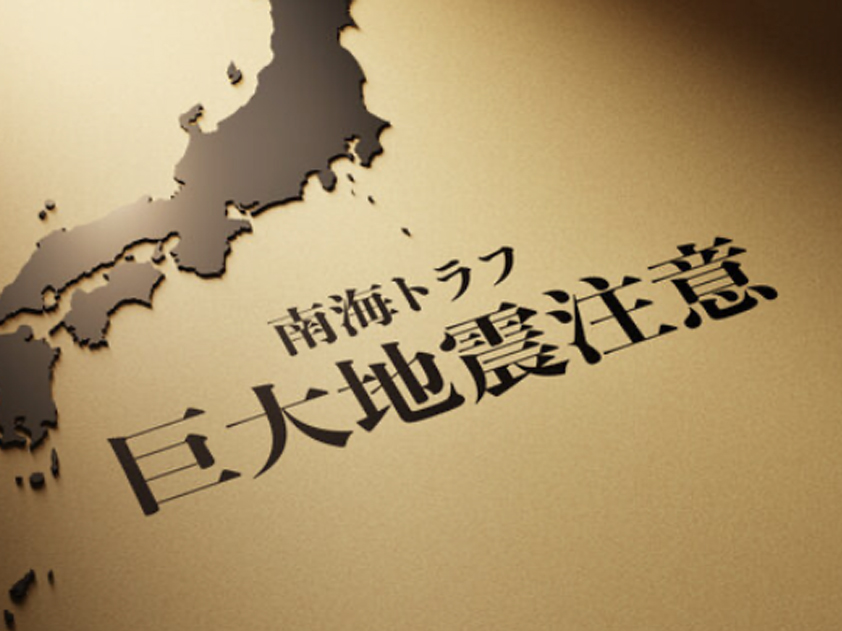南海トラフ地震臨時情報において最も切迫性が高い「巨大地震警戒」が発表された場合、全国で52万人を超える住民に1週間の事前避難が求められることが、内閣府の初調査で明らかになりました。
その半数以上は高齢者や障害者など配慮が必要な方々であり、自治体にとって避難所の不足や要配慮者の移動といった大きな課題が浮き彫りになっています。
津波が数分で到達する可能性のある地域が対象とされるため、国は臨時情報のガイドラインを改定し、海抜ゼロメートル地帯も事前避難の対象に加えるなど、避難準備の強化を図っています。
京都大学の矢守教授が指摘するように、国が人数を把握するだけでは不十分で、避難にかかる費用負担を含めた実効性のある支援体制が不可欠です。
日本は世界の陸地面積のわずか0.25%しか占めていないにもかかわらず、マグニチュード6以上の大地震の2割が集中するという、まさに災害大国なのです。
4つのプレートの境界に位置するという地理的宿命を背負い、南海トラフ地震や首都直下型地震といった巨大地震が「30年以内に高い確率で発生する」と予測されています。
その一方で、我が国の防災対策は必ずしも十分とは言えません。
とりわけ、財務省主導の緊縮財政が深刻な影響を及ぼしています。
かつて日本は公共投資をGDP比で見ても高水準に維持しており、地震リスクの低い欧州諸国と比較すれば、これは当然の政策でした。
しかし橋本龍太郎政権以降、公共投資は大幅に削減され、特に地方での防災インフラ整備に大きな影響を及ぼしました。
首都圏には相対的に手厚い投資が続いた一方で、地方では水害や土砂災害の被害が頻発し、防災格差が拡大しています。
国家の基本的責務である「国民の生命と財産を守ること」が、財政健全化の名のもとに軽視されてきた現実は厳しく指摘されねばなりません。
さらに問題なのは、財務省の一部官僚が「災害対策よりも財政余力の確保を優先すべきだ」と主張している点です。
能登半島地震の復興に際しても「人口減少を見据えた集約的なまちづくり」が提言されましたが、これは被災者の生活再建よりも経済合理性を優先した冷酷な姿勢と受け止められかねません。
災害に苦しむ地域を切り捨てる発想は、災害大国にふさわしい国家戦略とは到底言えないのです。
今後、国が進むべき方向は明確です。
第一に、防災・耐震化への投資を大幅に拡充し、過去の公共投資削減の過ちを正すことです。
第二に、地域で助け合う文化を国民全体で育むことです。
第三に、首都圏への過度な一極集中を改め、人口と産業を地方に分散させることです。
これは経済政策にとどまらず、国家安全保障の根幹に関わる課題です。
災害対策は短期的な経済効率性の尺度で測るべきものではなく、国家の存在意義そのものに直結するものです。
防災への積極的な投資は、将来の甚大な被害を未然に防ぐとともに、持続可能な社会を築くための必要不可欠な先行投資です。
南海トラフ地震をはじめとする巨大災害が現実の脅威として迫る今こそ、国は「国民を守る」という国家の原点に立ち返り、真に実効性のある成果を挙げるために、財政支出を惜しむべきではありません。