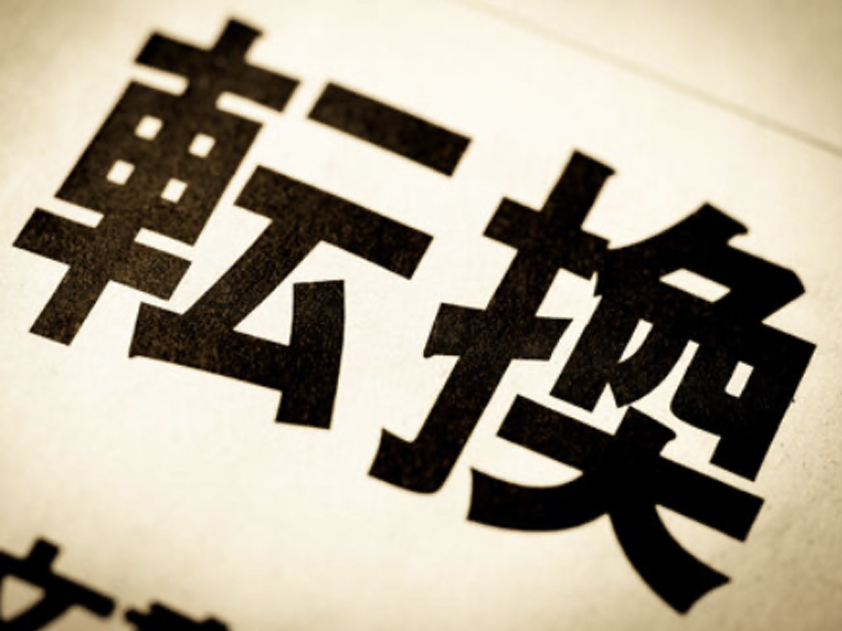日本の農政が大きな転換点を迎えています。
政府は令和7年8月5日、コメの安定供給に向けた関係閣僚会議を開催し、石破総理大臣はコメの増産と輸出拡大にかじを切る方針を表明しました。
この背景には、価格高騰の原因となった需給見通しの誤りや、備蓄米の放出の遅れといった問題を受け、耕作放棄地の拡大を食い止めながら農業を次世代につなぐ一応の転換意思が垣間見られます。
この転換は、長年にわたり日本の農業を衰退させてきた減反政策に対する、事実上の「失政認定」と言えるでしょう。
1970年代に始まったこの政策は、コメの過剰生産を抑える目的で導入されましたが、結果として農業従事者の離農と耕作放棄地の増加を招き、日本の食料自給率を著しく低下させました。
近年のインバウンド需要の増加や消費構造の変化を見誤った結果、国内のコメ供給は逼迫し、価格は高騰しました。
にもかかわらず、これまでの政府は減反政策を根本的に見直すことなく、備蓄米の活用も場当たり的なものでした。
このような現状を踏まえ、私はコメの増産とともに、「籾米(もみごめ)備蓄制度」の復活を提案します。
かつて日本では戦国時代から籾米による備蓄が行われてきました。
籾米は、籾殻に包まれたままの状態で保管されるため、長期保存に非常に適しています。
適切な環境下では数十年、場合によっては百年以上も発芽能力を保つとされ、まさにコメの命を守る「自然のカプセル」なのです。
籾米は、脱穀・精米すればそのまま主食として食用になり、さらに種籾としても利用できます。
加えて、籾殻や糠は肥料、飼料、土壌改良材、さらには燃料など多用途に再利用が可能であり、持続可能な農業と循環型社会を支える資源です。
流通させる精米と備蓄用の籾米を明確に区別し、消費用の精米は需給を見極めて調整しつつ、余剰米はすべて籾米として備蓄する体制を構築すべきです。
市町村、企業、そして各家庭においても籾米備蓄を促進し、いざというときに備えて食料確保を図る。
それこそが、真に持続可能で強靭な国家の基盤です。
現行制度には、この根本的な視点が欠落しています。
これは、高度経済成長期以降の経済優先政策の中で、食料の安全保障を独立国家の柱として捉え直す視点が不足していた結果と言えるでしょう。
江戸時代、飢饉に際して金銭はあるのに食料を買えず、多くの人が苦しんだという記録が残っています。
金銭への過信と他者への不信が、結局は命を救わなかったのです。
現代社会でもなお、カネで全てが解決できるという傲慢な合理主義が根強く残っています。
しかし、それは非常時にはたやすく崩れ去る幻想にすぎません。
豊かさとは、財政黒字をどれだけ溜め込んだかではなく、いかにして供給能力の「余力」を備えているかにあります。
食糧安全保障の観点から、私たちが目指すべきは「カネ持ち」ではなく、「コメ持ち」です。
コメこそが国の礎であり、国民の命を支える最も根源的な資源です。