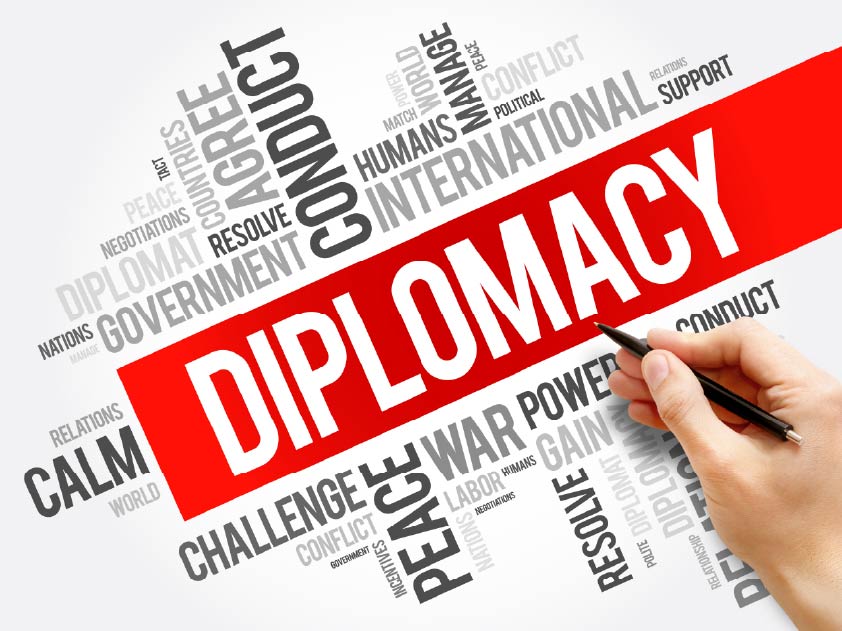日米関税交渉が難航するなか、トランプ大統領は7日、日本に対して25%の相互関税を課す方針を明らかにしました。
これを受け、石破茂首相は参院選の遊説で、従来にない強硬姿勢を示し、トランプ政権に言及しました。
街頭演説で「これは国益をかけた戦いだ。なめられてたまるか」と語り、さらに語気を強め、「たとえ同盟国であっても、言うべきことは正々堂々と主張しなければならない」と続けました。
日本の首相が同盟関係にある米国を相手に「なめられてたまるか」などと激しい口調で語るのは極めて異例のことであり、実に驚きました。
首相は10日に出演したテレビ番組で、こうした発言の意図について、安全保障や食料などにおける日米関係に触れながら、「いっぱい頼っているのだから言うことを聞きなさいということだとすれば、それは侮ってもらっては困りますということ」と説明しました。
しかしながら、首相の言葉の背後には、与党にとって厳しい選挙情勢が伝わるなか、交渉の不調が選挙戦に影響することを恐れる焦りの色もにじんでいるように見受けられます。
「なめられてたまるか」発言は、単なる驚きでは済まず、深い懸念を抱かざるを得ませんでした。
首相の発言は、国民感情に寄り添う意図があったとしても、外交の場においては不適切な言辞と評価せざるを得ず、結果としていくつかの重大な国益の毀損を招く可能性すらあります。
第一に、交渉力の低下です。
外交交渉は、相互の信頼と尊重を前提とするものです。
対決的で感情的な表現は、トランプ政権側に敵意や軽視の印象を与えるおそれがあり、結果として米国側が態度を硬化させ、交渉が非建設的なものとなり、さらには報復的な局面へと変質する懸念があります。
第二に、国内政治のパフォーマンス化による外交力の低下があります。
こうした発言が選挙目当てと受け止められれば、政権が実質的な交渉よりも支持率維持を優先していると映り、日本側の誠実さが疑われます。
それは即ち、日本の交渉力を著しく低下させる結果となります。
第三に、経済的な報復の誘発です。
トランプ政権の外交は「取引型」であり、非礼や挑発に対して敏感に反応する傾向があります。
この発言が逆鱗に触れた場合には、自動車関税の引き上げ、農産品市場の強制的開放要求、為替政策への圧力強化など、さまざまな不利益が現実のものとなるおそれがあります。
これらの措置が現実化すれば、日本経済に甚大な打撃を与えることは避けられません。
第四に、日本の国際的イメージの失墜です。
日本は長年にわたり、冷静で礼節を重んじる外交姿勢によって国際的な信頼を築いてきました。
そのような外交的品格は、目には見えないものの、きわめて重要なソフトパワーです。
軽率な言葉はその信頼を一挙に損ないます。
第五に、国内外の分断の助長です。
このような勇ましい発言は、国内の一部世論には訴える力があるかもしれませんが、結果として国論の分断や、冷静で現実的な外交政策の形成を困難にします。
また国際社会においても、「内向きなナショナリズム国家」と見られる危険性が高まります。
今回の石破首相の発言は、発言の内容のみならず、その発せられた「場」においても大きな問題があります。
政府首脳の発言は、たとえ国内向けであっても、国際社会では外交的メッセージとして厳しく受け止められます。
特に選挙演説のような公開の場における発言は、相手国の政府やメディアも必ず注視しており、日本政府の公式見解と見なされかねません。
だからこそ、外交上のリスクを伴う発言は、非公式な会議や関係閣僚による非公開の協議の場でこそ行うべきなのです。
勇ましい演説が一時的に票を得ることがあっても、その結果として外交関係の信頼を損なえば、その代償として中長期的な国益の低下を招くおそれがあります。
リーダーには、短期的な喝采よりも、国家全体の利益を見据えた冷静さが求められます。
石破首相は7月10日、テレビ番組で「日本は安全保障やエネルギーなどにおいて米国への依存からもっと自立しなければならない」とも語りました。
これに対して米国務長官は、「それを否定的にとらえるべきではない。日米関係は非常に強固であり、日本の軍事力の向上はむしろ励みになる」との前向きな姿勢を示しました。
この反応の真意はさておき、米国側が冷静かつ前向きに対応していることと比べると、首相の「なめられてたまるか」という発言が外交的に未熟であったことは否めません。
国家指導者の発言一つひとつには、国の信頼と尊厳がかかっています。
発言の場と内容をわきまえた成熟した言論こそが、国民の負託に応える政治のあるべき姿です。