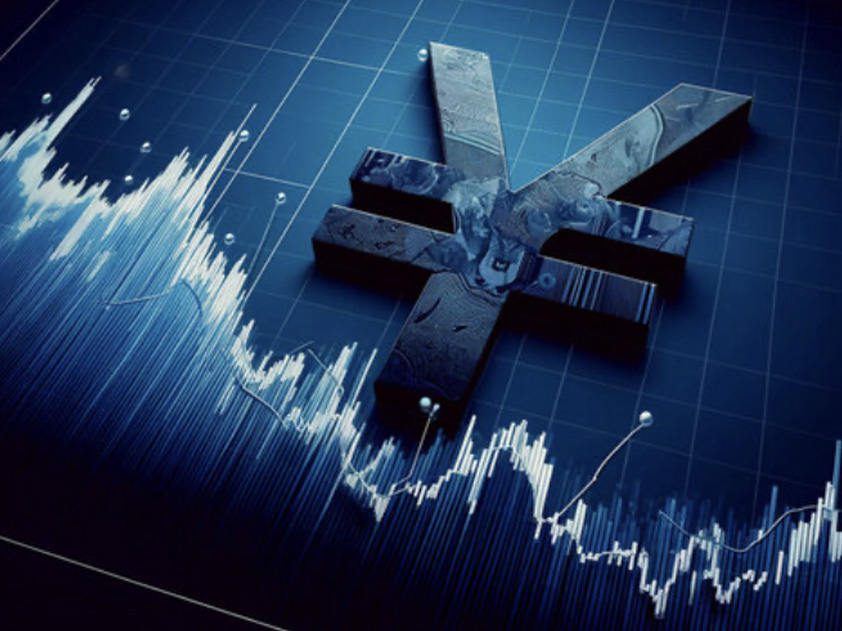週刊文春の報道によれば、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長が、高市早苗首相に対し、「円危機が始まった」と警告するメッセージを送っていたことが明らかになりました。
三木谷氏は、①財政支出の拡大が財政悪化への懸念を招き、円危機につながること、②富裕層への課税強化がキャピタルフライトを引き起こすこと、③円の価値はすでにドルベースで半分になっており、この流れが続けばインフレが加速すること、以上の点を問題視したとされています。
しかし、私は、①②③のすべてについて反論します。
三木谷氏の指摘は、“市場からどう見えるか”という話であって、“国家が通貨をどう成立させているか”という議論ではありません。
まず、「財政ばらまきが円危機を招く」という点について反論します。
財政支出が増えれば、為替が動くことはあります。
しかし、財政支出が増えたという事実だけで、通貨が危機に陥るわけではありません。
通貨危機とは、給料の支払い、商取引、税の納付といった日常の経済活動において、その通貨が使えなくなる事態を指します。
現在の日本で、円が使えなくなっているでしょうか。
答えは明らかに違います。
円は、日本という国家が発行し、法律で通用力を与え、税を円で徴収する国家通貨です。
自国通貨建てで財政支出を行い、自国通貨建てで国債を発行している限り、財政支出の拡大それ自体が通貨危機を引き起こすことはありません。
問題が生じるとすれば、それは財政の「量」ではなく、国家としての通貨運営に一貫性が失われた場合です。
次に、「富裕層課税でキャピタルフライトが起きる」という指摘についてです。
ここでは、通貨の信用が何によって支えられているのかを正確に理解する必要があります。
円の信用は、富裕層が日本に住み続けるかどうかで決まるものではありません。
投資家の機嫌によって支えられているものでもありません。
円の信用を支えているのは、日本という国家が、税を円で徴収し、支払いを円で行い続けるという制度です。
仮に一部の富裕層が国外に資産を移したとしても、それだけで円が使えなくなることはありません。
給料は円で支払われ、買い物は円で行われ、税金は円で納められ続けます。
通貨とは、こうした日常の制度の中で使われ続けることで成立しているものです。
「富裕層の信認」が円の価値を決めるという考え方は、通貨を国家制度ではなく、金融商品のように扱う発想に基づいています。
三つ目に、「円の価値はドルベースで半分になった」という指摘についてです。
確かに、為替レートは大きく変動しています。
しかし、為替レートは通貨の価値そのものではありません。
為替は、あくまで二国間の相対価格であり、金融政策や国際環境の影響を強く受けます。
円安になったからといって、円が国内で通貨として機能しなくなったわけではありません。
円は依然として、決済手段であり、価値尺度であり、納税手段です。
為替の下落と通貨危機を同一視することは、概念の混同です。
では、なぜ円安が進んでいるのか。
その最大の要因は、日米をはじめとする諸外国との「金利差」であって、「円の信認」などではありません。
高金利通貨が買われ、低金利通貨が売られるという、ごく教科書的な資金移動が起きているにすぎないのです。
三木谷氏が指摘する三つの点に共通しているのは、「市場の反応」をもって通貨の安定性を測ろうとしている点です。
しかし、現代の通貨は「価値のあるモノ」ではなく、「信用」、すなわち負債の体系として成立しています。
銀行預金は銀行の負債であり、国債は政府の負債です。
その信用の体系の最上位にあるのが、国家が発行する自国通貨です。
本当の意味での円危機が起きるとすれば、それは財政支出が増えたときでも、富裕層が動いたときでも、為替が下がったときでもありません。
国家が、自国通貨をどのように支え、どのように運営するのかについて、政府と中央銀行の間で一貫した意思を失ったときです。
円危機とは、財政の大小の問題ではなく、通貨を運営する国家の統治が揺らいだときに起きる現象なのです。
三木谷氏の指摘は、「市場はこう反応する」という警告としては理解できます。
しかし、それをそのまま「円危機」と呼ぶのであれば、通貨の成立構造を取り違えています。
いま本当に問われているのは、財政を出すか出さないかでも、誰が国外に資産を移すかでもありません。
日本という国家が、円という通貨をどのような原理で運営し続けるのか。
その一貫した意思こそが、円の安定を左右する最大の要因なのです。