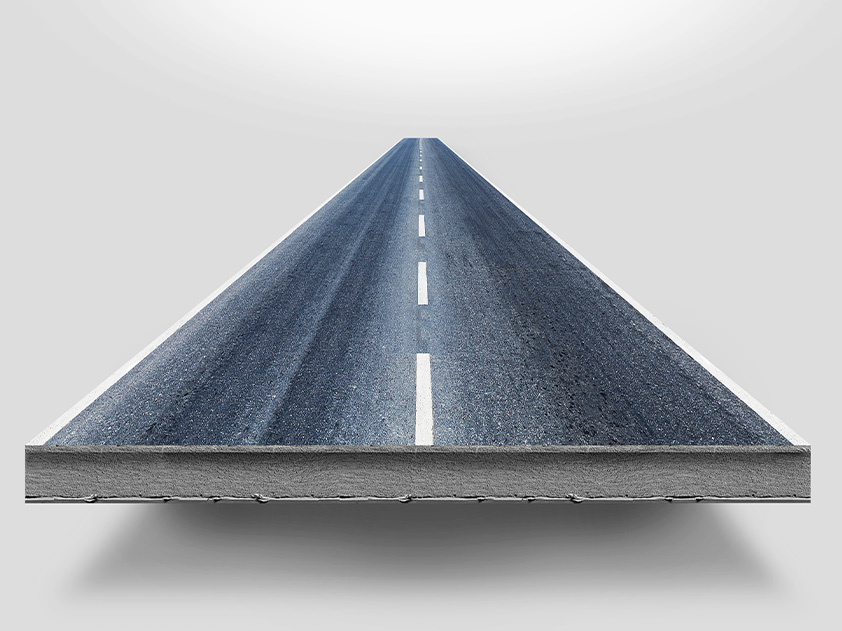本市の第2次道路整備プログラムは、渋滞対策や交通安全対策など、市民生活に直結する重要な社会資本整備を担う計画です。
しかし、その進捗を冷静に見ていくと、事業の遅延が一時的・例外的なものではなく、むしろ慢性化している現実が浮かび上がります。
たとえば、後期①では完了予定11工区のうち5工区が未達成、後期②でも16工区中9工区が未達成見込みとされており、計画全体として「遅れ在りき」の状態に陥っていることは否定できません。
にもかかわらず、公式な説明では「用地交渉の難航」や「施工方法の見直し」といった一般論が繰り返され、なぜ同様の遅延が長期にわたり再生産されているのか、その根本原因は十分に説明されてきませんでした。
この点を明らかにするため、私は令和7年12月19日の議会質問で、個別の現場対応ではなく、道路整備を取り巻く制度と財政構造そのものに焦点を当てました。
まず明らかになったのは、本市に限らず、地方自治体の道路整備が国庫補助金に極めて強く依存しているという事実です。
建設緑政局長の答弁によれば、第2次道路整備プログラム開始以降の約10年間、市債や一般財源のみで事業化された路線は一つもなく、国庫補助が得られなければ、着手できなかった路線が複数存在したとされています。
また、財源構成を見ると、国庫補助の割合は年々低下傾向にある一方で、市債の割合は上昇を続けています。
直近の年度では、市債が事業費の6割を超える年度もあり、地方自治体が自らの判断で事業量を調整できる余地は、実質的に極めて限定されています。
さらに、一般財源のみでの市単独事業については、「財政負担が過大であり、現行制度の下では極めて困難」と明確に答弁されています。
国庫補助が得られない場合、市債で補えばよいという単純な話ではなく、起債には償還可能性や財政健全化指標といった別の制約が重くのしかかります。
ここで重要なのは、「B/C(便益/費用)が低くて採択されなかった路線はない」という答弁の意味です。
一見すると問題がないようにも見えますが、裏を返せば、費用便益比が低くなりやすい路線は、そもそも計画段階で位置付けを見送られている可能性を示しています。
つまり、必要性が高くても、評価制度に適合しない事業は最初から俎上に載りにくいという構造が存在しているということです。
この評価制度の中核にあるのが、「社会的割引率」を前提とした費用便益分析です。
長らく4%という高い割引率が用いられてきた結果、将来世代にもたらされる便益は大きく割り引かれ、公共事業のB/Cは低く算定されやすくなってきました。
財政局長の答弁では、国の委員会において社会的割引率の妥当性が見直しの議論対象となっており、仮に引き下げられれば、費用対効果が高まり、国庫補助の基準を満たしやすくなる可能性が示されています。
しかし、ここで問われるべきは、単に割引率を何%にするかという技術的な問題ではありません。
社会的割引率そのものが、政府財政を家計や企業と同様の制約下に置く「家計簿的な財政観」を前提とした概念であり、通貨主権を有する国家の財政運営の現実とは整合していない点こそが、本質的な問題です。
この誤った前提に基づく評価制度と、プライマリー・バランス黒字化目標に象徴される緊縮的な財政運営が組み合わさることで、自治体の必要なインフラ投資は、補助採択や起債判断を通じて制度的に抑制されてきました。
道路整備の遅延は、用地交渉や現場努力の問題というよりも、まさにこの構造制約の帰結であると捉えるべきです。
本市の道路整備の遅れは、川崎市固有の問題ではありません。
同様の評価基準と財政制度の下にある全国の自治体が、同じ制約に直面しています。
だからこそ、社会的割引率を含む公共事業評価体系や、プライマリー・バランス黒字化目標そのものについて、地方自治体の立場から正面から問題提起し、国に改善を求めていく必要があると考えます。
インフラは、将来世代に引き継がれる公共の資産です。
その価値を過小評価する制度の下で投資を先送りし続けることが、果たして持続可能な財政運営と言えるのでしょうか。
今回の議会質疑は、その根本的な問いを改めて突きつけるものとなりました。