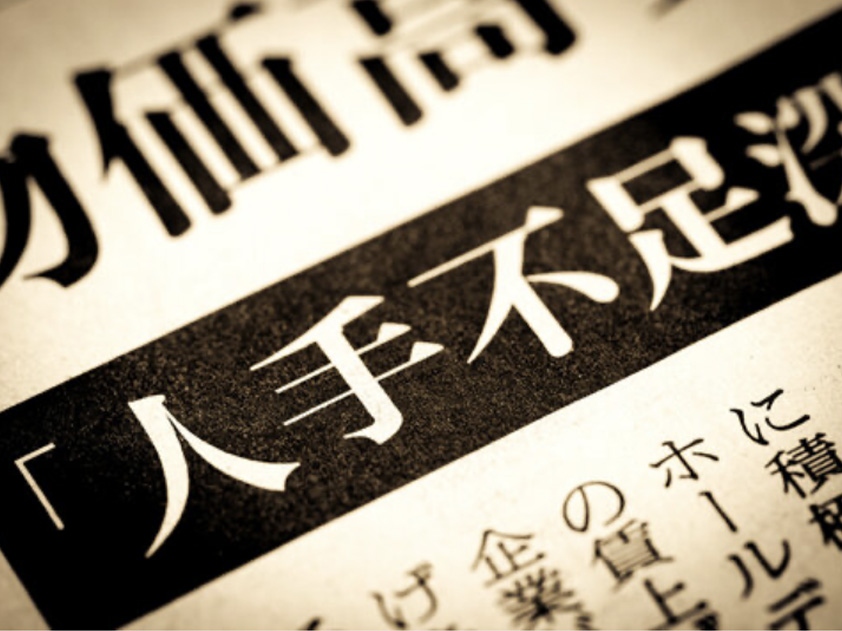政府は2026年に、労働基準法を約40年ぶりに大改正しようとしています。
「長時間労働の是正」「休息時間の確保」「働きやすい社会の実現」という理念が掲げられており、一見すると正しい改革のように聞こえます。
その理念自体を否定はしません。
しかし、理念を支える現実が整っていなければ、どれほど立派な制度も現場を苦しめるだけです。
現場にしわ寄せが集中し、むしろ働き方が悪化するおそれがあります。
残念ながら今回の改正は、その典型例だと考えます。
政府の目的は、労働者を休ませ、心身の健康を守り、ワークライフバランスを向上させたいというものです。
多くの人が望む方向性でしょう。
しかし、休むためには人手の余裕、生産性の高さ、業務量の削減、コスト増を許容できる経営余力が必要です。
ところが現実には、歴史的な人手不足と供給力の低下が進んでおり、休ませる余力そのものが存在しません。
それでも制度だけ先に整えられると、対応できる業界とできない業界に分かれ、格差が固定化してしまいます。
大企業やIT業など余力のある業界は制度を守ることができますが、とりわけ医療や介護、保育、物流、外食、小売など生活インフラを支える現場は、制度に適応できず疲弊していきます。
最も守るべき現場が、最初に壊れてしまうのです。
政府には休ませたいという思いがあります。
制度として休ませる仕組みも作ろうとしています。
しかし、現場には休ませられるだけの余力がありません。
制度と現実の乖離を放置したまま理念だけを法で上塗りしても、うまく機能するはずがありません。
理念を実現するには、まず構造を整える必要があります。
生産性の向上、供給力の回復、人材育成、公共性の高い業種への重点的な投資。
こうした現場を支える政策こそが先決です。
それを怠ったまま、制度だけを先に改正すれば、現場の崩壊を加速させるだけです。
現実を無視した改革には、必ず現実が報復します。
今回の労基法改正は、「人にやさしい働き方改革」というより、「現場に厳しい働かせ方改革」になりかねません。
現場なき制度設計こそ、2026年労基改正の象徴です。
政策において最も大切なのは、理念だけではなく実態です。
現実を見ない改革は、国を破綻させます。
いま必要なのは、現実から出発する労働政策です。