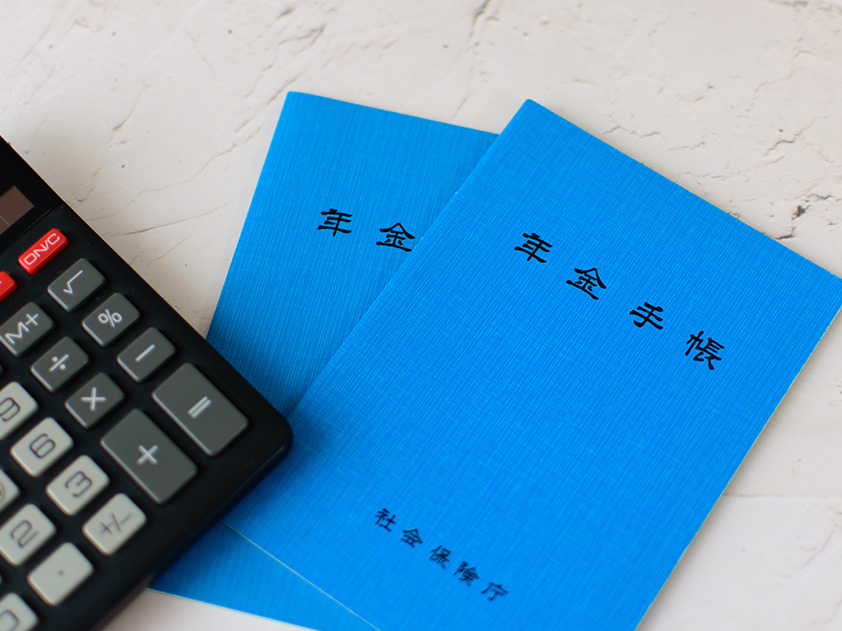高市政権のもとで新たに設置された「成長戦略会議」。
そのメンバーの一人に、クレディ・アグリコル証券のチーフエコノミストである会田卓司氏が選ばれました。
金融市場にも精通し、マクロ経済分析の第一人者として知られる会田氏の積極財政論に大いに期待をするところです。
さて、その会田氏が我が国の年金制度について次のように解説されています。
・日本の公的年金制度は「賦課方式(Pay as you go)」を採用しており、現役世代の保険料と税収によって、その時点の高齢者の年金を賄う仕組みになっている。
・過去の人口ボーナス期に積み上げられた積立金があり、それは将来のための“貯金”ではなく、制度を安定させるための「予備的資金」である。
・この積立金が存在するからこそ、日本の年金財政は他国よりもはるかに健全である。
なるほど、一見すると、冷静で理路整然とした説明のように聞こえます。
しかし、その説明には一つの思想的限界があります。
それは、会田氏の議論はあくまで「税や保険料を財源として制度を支える」という、近代的な“租税国家パラダイム”の中にとどまっているという点です。
つまり、年金制度の持続可能性は「経済成長による税収増」や「現役世代の負担能力」に依存すると言うわけです。
この発想は、「国家はおカネを集めて支出する存在である」という、家計簿的な財政観に立脚しています。
そのため、会田氏の議論では「経済成長が続く限り制度は破綻しない」と結論づけられますが、裏を返せば「成長が止まれば破綻する」ということにもなります。
これでは、制度そのものは守れても、制度を支える経済の構造までは救えません。
残念ながら、会田氏が論じているのは“制度を守るための経済論”であって、“経済そのものを再生させる論”ではないのです。
当該ブログで繰り返し述べているとおり、税は財源ではありません。
したがって、年金制度は「国民経済を循環させる装置」として位置づけられるべきです。
政府は自国通貨を発行できるのですから、年金の支払いに必要な資金は、税収や保険料によらず、国債発行によって支出すればよい。
むしろ、経済を再生させる具体策として、年金を倍増すべきなのです。
例えば、年金を倍増すれば、高齢者の生活に余裕が生まれ、消費が増え、需要が拡大し、それが現役世代の所得を押し上げます。
「誰かの支出は、必ず誰かの所得になる」という経済の基本原則に立脚すれば、当然の帰結です。
この“支出=所得”の循環を取り戻すことこそが、真の成長戦略です。
会田氏の年金論では、年金の増額は“財源の裏づけ”がなければ難しいことになります。
問われるべきは、制度をどう維持するかではなく、その制度を支える経済をどう蘇らせるかという視点です。
自国通貨建てで国債(通貨)を発行できる国家において、政府支出の制約は「財源」ではありません。
政府の支出が需要を生み、需要が生産を支え、生産増が結果として税収を増やします。
この循環を取り戻すことでこそ、年金も社会保障も持続します。
「財源がない」という言葉に縛られる限り、私たちは制度を守っているようで、実際には経済の循環を止めています。
制度を救うために国民が犠牲になる社会から、国民を救うために制度を活かす社会へと転換しなければなりません。