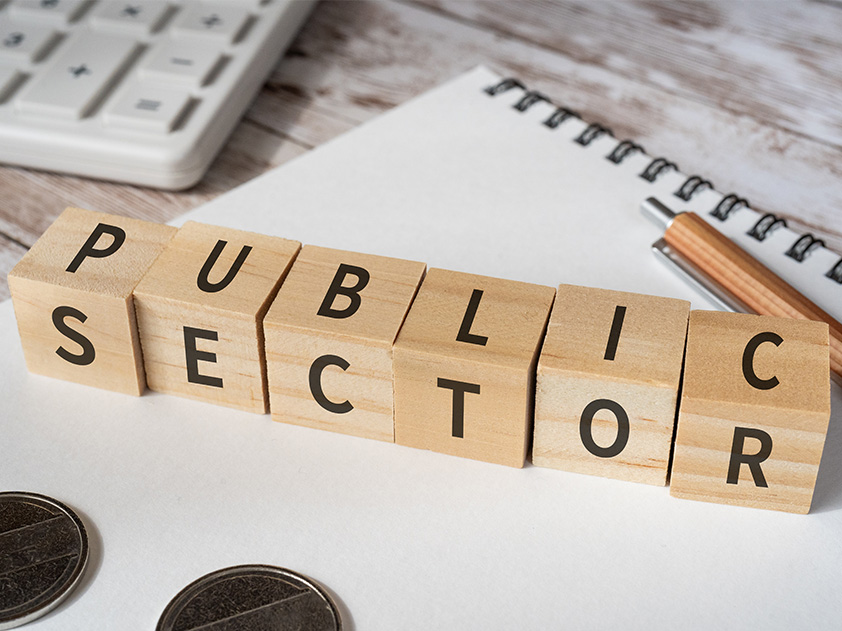防衛省が2021~23年度に発注した自衛隊および在日米軍施設の建設工事で、入札不調対策として適用されている「見積もり活用方式」の運用に重大な問題があることが、会計検査院の調査で明らかになりました。
同検査によれば、214件のうち9割超にあたる196件で、適用する具体的な根拠が不明確でした。
さらに全件で、見積金額の妥当性を確認できず、過大積算の恐れがあるとされています。
つまり、防衛省が「なぜその価格で契約したのか」を説明できない事例が大半を占めていたということです。
この背景には、単なる事務上の不備を超えた、構造的な問題があります。
それは、長年にわたる「緊縮財政」と「ネオリベラリズム(新自由主義)」に基づく政策が、行政の積算能力と建設業界の供給力を同時に蝕んできたということです。
かつて、役所には建設・土木・電気設備といった各分野の技術職員が在籍し、入札価格を積み上げる「積算の力」を持っていました。
ところが、「行政のスリム化」や「民間活力の活用」といった掛け声のもとで、設計・積算業務の多くが外注化されていきました。
これこそが、いわゆる外注主義です。
外注主義が進めば、行政は「自分で積算できない」体質になります。
結果として、業者から提出された見積書をそのまま受け入れるしかない構造が生まれます。
会計検査院の指摘した「根拠不明」「妥当性の確認不能」は、その帰結にほかなりません。
一方で、ネオリベラリズムに基づく緊縮予算は、公共事業費を削り続けてきました。
それにより、地方の建設会社は採算の取れない仕事を避けざるを得ず、廃業や撤退が相次ぎました。
若い技能者が育たず、建設現場の供給力そのものが損なわれていったのです。
この二つの要素――行政の積算力の衰退と、民間の供給力の喪失――が組み合わさった結果、入札不調が常態化しています。
いくら予算を確保しても、応札してくれる業者がいない。
まさに「予算はあるのに工事ができない」という異常な状況が、各地で現実のものとなっています。
私はかねてより、川崎市議会の場でもこの問題を指摘してまいりました。
行政がこのまま「外注」と「緊縮」の二重構造を続ければ、やがては「おカネがあっても公共事業ができない」時代が来ると。
そして案の定、それがいま現実になろうとしています。
公共事業とは、本来、国民の安全と生活を守るための基盤整備です。
それを支える行政と建設業界が、緊縮と外注によって弱体化してしまえば、国家の実行力そのものが失われます。
財政を締め上げ、行政を痩せ細らせることが、”改革”ではありません。
真の改革とは、公共を担う力を取り戻すことです。
そのためには、積算・設計・施工の三位一体を再構築し、行政が本来持つべき技術的能力を取り戻さなければなりません。