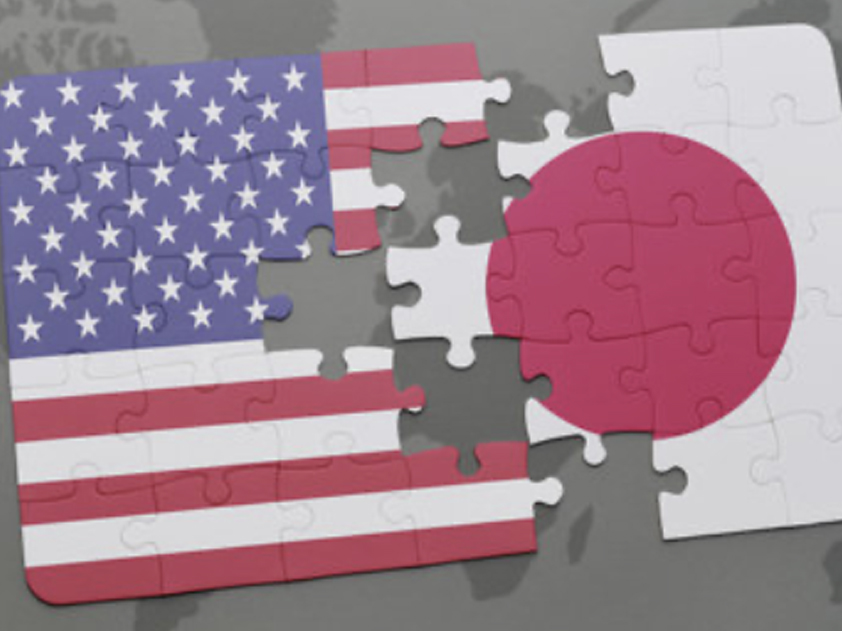80年前の今日、1945(昭和20)年8月14日、日本政府はポツダム宣言を受諾し、我が国の敗戦が正式に確定しました。
同日、この受諾に関する「終戦の詔書」が発せられ、翌15日にはラジオ放送(玉音放送)を通じて国民に伝えられ、16日からは日本軍の武装解除が始まりました。
しかし、8月18日、ソ連軍が千島列島最北端の占守島(しゅむしゅとう)に突如上陸。
停戦命令を受けていた日本守備隊は侵攻軍に応戦し、激しい戦闘が展開されました。
もしソ連が占守島を占領していれば、そのまま北海道へ侵攻した可能性が高く、この戦闘は本土防衛上、極めて重要な意味を持ちました。
結果、日本軍はソ連軍に甚大な損害を与えました。
では、8月14日のポツダム宣言受諾と、それに基づく9月2日の戦艦ミズーリ艦上での降伏文書調印において、日本政府はいかなる法的根拠で臨んだのでしょうか。
答えは、大日本帝国憲法第13条に定められた「講和大権」です。
1951(昭和26)年11月8日にサンフランシスコ講和条約を締結し、我が国は主権を回復しましたが、その法的根拠も帝国憲法第13条(講和大権)にありました。
交戦権を否定する現行憲法(占領憲法)では主権回復は不可能であり、帝国憲法が存続していたからこそ日本は独立できたのです。
戦後、「日本は無条件降伏した」と誤解されがちですが、ポツダム宣言が定めたのは「日本軍隊の無条件降伏」であり、「日本政府(日本国)の無条件降伏」ではありません。
我が国は、ポツダム宣言という明確な条件のもとで降伏したのです。
したがって、ポツダム宣言に明記された以外の条件を受け入れる義務は、本来ありませんでした。
しかし現実には、原爆による恫喝のもと、占領憲法を押し付けられたのです。
GHQが日本政府に占領憲法の原案(マッカーサー・ノート)を突きつけたのは、1946(昭和21)年2月13日のことです。
この日、当時六本木にあった吉田茂外相公邸で、日米の秘密交渉が行われました。
交渉開始からわずか10分後、GHQ草案が日本側に手渡され、「よく読め」と言わんばかりに、GHQ高官のホイットニーは部下とともに部屋を出て庭へ向かいました。
庭に出てから15分ほど経つと、そこに吉田の側近・白洲次郎が現れました。
そのとき、ちょうど上空を米軍機が爆音を響かせながら飛び去っていきました。
空を見上げたホイットニーは、物静かにこうつぶやきました。
「我々はこの庭で、原子力の光で暖をとっているのだよ」と。
ホイットニーが日光浴をあえて「Atomic Energy」と表現したのは、明らかに「広島と長崎を忘れるな」という脅しでした。
これは、我が国の戦後が「脅し」によって始まったことを示す象徴的な場面です。
法的正統性を欠き、脅しによって強制された占領憲法を、我が国はいまも憲法として戴いています。
この事実に異を唱える国会議員は、一人として存在しません。
このような国会議員たちに「法の支配」を語る資格はありません。