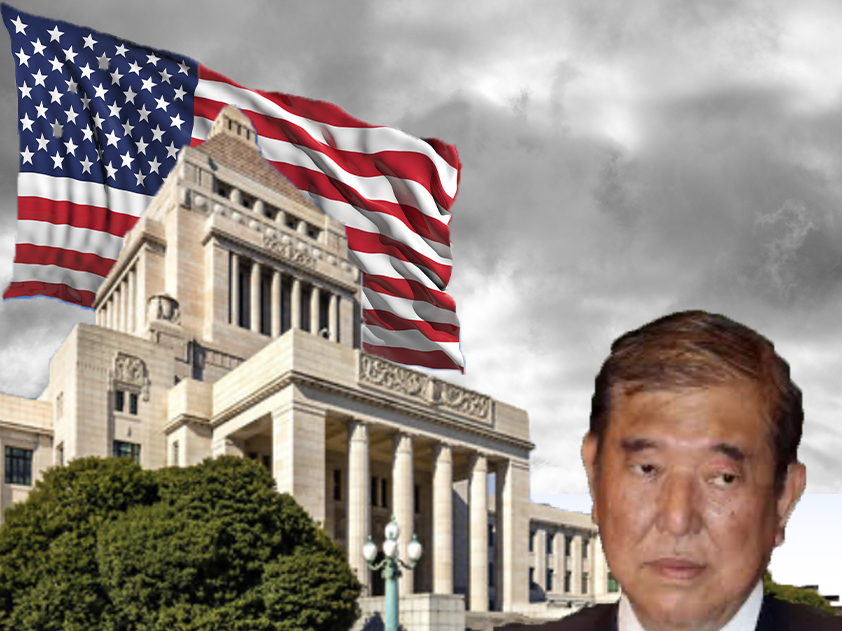去る令和7年6月19日、私は川崎市議会において、志を同じくする無所属の議員と共に、ある意見書案を提案いたしました。
それは、地方自治法第99条に基づき、地方議会が国に対して意見を具申できる制度を活用したもので、日本の将来に深く関わる重要な提案であったと自負しております。
その内容は、「大日本帝国憲法を復元し、現行憲法を無効とした上で、新たな憲法を制定していただきたい」というものでした。
憲法とは本来、国家の主権が発動されて初めて、その正当性が担保されるものです。
ところが、現行憲法は、我が国が主権を喪失したまま連合国に占領されていた時代に、連合国軍総司令部(GHQ)の主導のもとで制定されたものです。
そのような憲法に法的な正統性があるわけがありません。
多くの方からは「改正すればよいのではないか」という声もいただきます。
しかし、占領下で定められた枠組みの中でいくら改正を繰り返しても、それはあくまでマッカーサーの描いた枠の内側でもがいているに過ぎず、現行憲法を「最高法規」として崇め続ける限り、私たち日本国民は、いつまでも「隷属国民」の立場から抜け出すことはできません。
たとえば、その象徴ともいえるのが、「横田空域」の存在です。
東京・横田基地を起点とし、神奈川、埼玉、群馬、栃木、福島、新潟、長野、山梨、静岡の1都9県にまたがる広大な空域が、今なお米軍の管理下に置かれています。
この空域では、日本の民間機や自衛隊機でさえ、米軍の許可なしには自由に飛行することができません。
羽田空港に着陸する旅客機が千葉県側を大きく迂回しているのは、この空域の制限によるものです。
驚くべきことに、このような重大な制限には、我が国の憲法にも国内法にも根拠がありません。
その法的な支えとなっているのは、「日米地位協定」や「日米合同委員会における合意」といった、いわゆる条約や国際的な取り決めなのです。
つまり、現行憲法が「最高法規」とされているにもかかわらず、実際にはその上に条約が存在し(現行憲法第98条2項)、さらにその上に米国という国家があるという、いびつな主従関係が現実のものとして存在しているのです。
そもそも、米国という国は、条約と国内法が矛盾した場合には、国内法を優先させるという原則を明確に持っています。
合衆国憲法第6条は「条約も合衆国の最高法規である」と定めておりますが、それはあくまで連邦法と整合性がある場合に限られ、矛盾する場合には国内法が優先されるという立場を、同国の最高裁判例も支持しています。
したがって、米国においては条約が自国の主権を脅かすことはありえず、日本が米国と締結した条約は結果として日本にとって不平等な内容にならざるを得ないのです。
TPPやFTAといった経済連携協定も、こうした条約優先構造の中で締結され、日本に不利な条件が組み込まれやすいという構造的な問題を抱えています。
こうして日本では、憲法よりも条約が優先されるという構造こそが、不平等の温床となっているのです。
日本の食料自給率が深刻なまでに低下しているのはなぜか?
それは、「MSA協定」という戦後の軍事援助に関する条約が憲法の上に存在しているからです。
日本の国土が外国人により際限なく買収されているのはなぜか?
それは、「GATS協定(サービス貿易に関する一般協定)」という条約が憲法の上にあるからです。
今の憲法を「最高法規」として認め続ける限り、私たちは未来永劫、「属国の民」として生きるしかありません。
そして、こうした主権の空洞化を放置すれば、やがて日本は中華人民共和国の勢力圏に組み込まれ、「日本人自治区」となってしまうような未来すら現実味を帯びるのです。
それは決して杞憂ではなく、経済・軍事・情報といった多方面から静かに進行している現実なのです。
だからこそ、私たちが川崎市議会で提出した意見書案は、極めて重大な意義をもつ提案だったと確信しています。
しかしながら、残念なことに、自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党、共産党、日本維新の会といった既成政党は、ことごとくこの提案に反対の立場を取りました。
この事実は、もはや既成政党の枠組みでは、日本の主権と尊厳を回復することは不可能であるという現実を示しています。戦後体制の中で利益を得てきた政党たちは、その構造から脱する意思を持ち得ないのです。
私は、この国の主権と誇りを取り戻すために、これからも声を上げ続けてまいります。
私たち自身の手で、真に自立した日本を築くために。