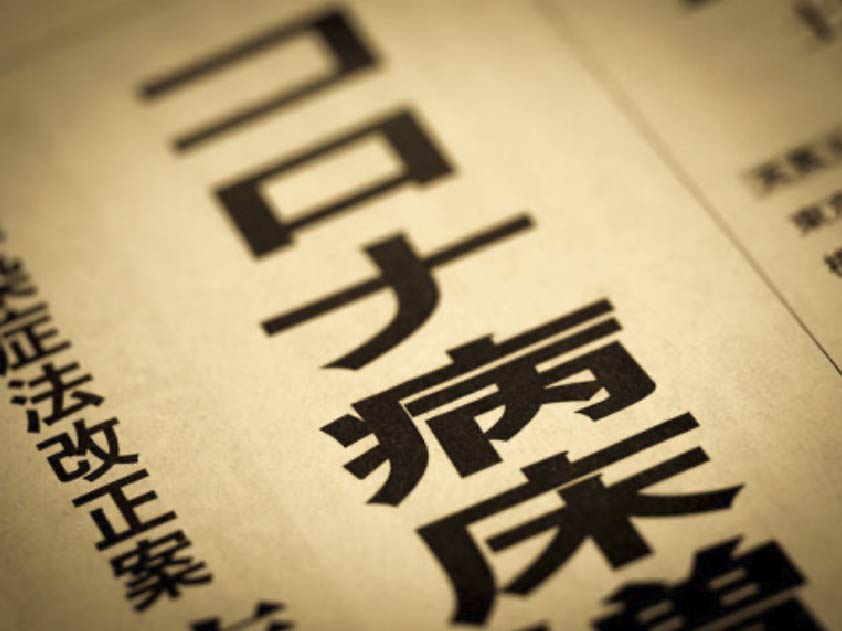今から7年前の2018年、川崎市は地域医療の将来を左右する極めて重大な判断を迫られる局面に直面しました。
葵会という医療法人社団から、「2020年東京オリンピックまでに、100床の外国人専用医療ツーリズム病院を市内に開設したい」との提案が寄せられたのです。
当初、この計画はインバウンド需要の高まりを背景に、観光と医療の融合として注目されました。
しかしながら、その裏には、地域医療の資源を損なう危険性が潜んでいたのです。
この提案を受けて、同年9月には川崎地域医療構想調整会議において、行政が概要を報告し、葵会は川崎市医師会・病院協会に対して説明を行いました。
さらに同年12月には、神奈川県議会が「医療ツーリズムの健全な発展と地域医療の確保に係る国の総合的な取組を求める意見書」を提出しました。
そして平成31年3月、川崎市もまた、衆参両院議長や関係閣僚に対し「医療インバウンド政策と地域医療構想の整合を図るため、関係法令や制度整備を速やかに進めるよう求める」要望書を提出しました。
この要望書からも明らかなように、当時の川崎市は、「外国人向け医療ツーリズム病院の開設を認可すべきか否か」について、まさに戸惑いと混乱の中にあったといえるでしょう。
私は当時、川崎市議会の健康福祉委員会に所属しておりました。
日本国民たる川崎市民のための貴重な病床資源を、富裕層外国人向けの医療ビジネスのために充てることに対して、強い疑念を抱いておりました。
そして平成30年9月25日の決算審査特別委員会において、私は外国人専用医療ツーリズム病院の開設に反対の立場から質疑に立ち、行政当局に対して以下のような点を質しました。
・当該病院は基準病床数制度のもとで認可される可能性があるのか
・将来的に日本人向け保険診療に移行される可能性はあるのか
・外国人向け病床が既存病床数に加算されるのか
・結果的に、地域の病床過剰状態が悪化しないか
行政側からの答弁では、外国人専用病院であっても既存病床としてカウントされるため、地域における新規病床の整備が一層困難になることが明らかになりました。
また、自由診療であれば日本人に対しても医療を提供することが法的に可能であり、それを制限する手立ては存在しないという答弁もありました。
このように、外国人専用をうたっていても病床は医療法上の病床規制の対象となり、市民のための医療資源が削られる可能性が極めて高かったのです。
さらには、これは当時から私が指摘していたことですが、川崎市南部医療圏では療養病棟入院の自己完結率はわずか38.02%で、市民の多くが他の医療圏の病院に頼らざるを得ない状況でした。
その状況は、今なお改善されていません。
すなわち、限られた病床を川崎市内で有効に活用していくことが求められてるなか、なぜ外国人専用の新たな病院を開設する必要性があったのでしょうか。
私は市議会において、「国民のための地域医療を犠牲にしてまで、外国人向け医療ビジネスを優先することは、市民の健康と命を軽んじる行為に他ならない」と強く訴えました。
当時、神奈川県の黒岩祐治知事は医療ツーリズム推進の立場を明確にしていましたが、私はその方針に真っ向から異を唱える立場をとったのです。
川崎市議会において、国民医療の観点からこの件に対して反対の立場を明確に表明した議員は、私ひとりであったと認識しております。
最終的に、葵会による外国人専用医療ツーリズム病院の開設計画は白紙となりました。
そして、その直後に新型コロナウイルス感染症の世界的流行が起きました。
川崎市内でも病床不足が深刻化しましたが、幸いにもコロナ病床の約4割を市立病院の病床で賄うことができました。
もしも、あのとき100床もの病床が外国人専用医療ビジネスに充てられていたならば、川崎市のコロナ対応は著しく困難なものとなっていたことでしょう。
限られた医療資源を、誰のために、どのように使うのか。
まさにこの判断こそが、行政の責務であり、議会の使命であると考えます。
外国人医療そのものを否定するものではありませんが、まず守られるべきは、日本国民、そして川崎市民の命と健康であるべきです。
あのとき、私が川崎市議会にいなければ、外国人向け医療ツーリズム病院の開設計画は粛々と進行していたかもしれません。
なお、今回の件を通じて明らかになったのは、自由診療と病床制度の間にある制度のほころびであり、今後、医療法や医療計画のあり方自体を見直す必要があると考えます。
「無所属」という小さな議席であっても、大きな誤りを食い止める力はある──私はこの経験を通じて、そう確信するに至りました。