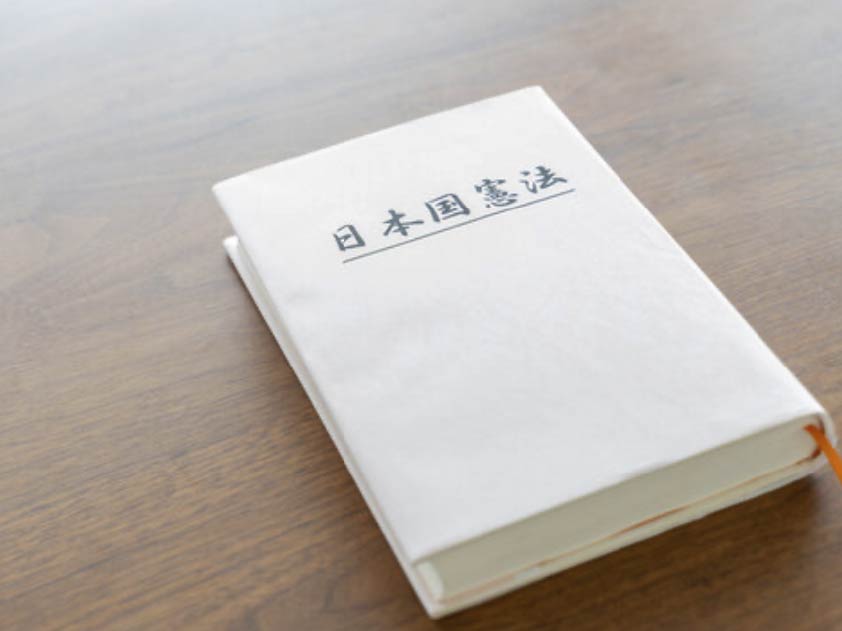国民の祝日に関する法律によれば、きょう5月3日は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」らしい。
ことしも全国各地で、改憲の必要性を説く集会、護憲の必要性を説く集会がそれぞれに開催されることでしょう。
私は改憲派にも護憲派にも属さない。
改憲派にしろ、護憲派にしろ、彼らに共通しているのは憲法議論の中心が「9条」にある点ですが、この憲法はそもそも前文からしておかしい。
ご存知のとおり前文には、日本国民は平和を愛する諸国民を信頼して、自分の生存を他国に委ねるとあります。
戦争はしない、軍備は持たないという憲法9条は、自分の生存を他国に委ねるという前文から導き出される当然の帰結なのです。
自分の生存を他国に委ねる…
論ずるのもバカバカしいが、これが独立した国家であるわけがない。
他人任せの姿勢を前文で恥ずかしげもなく謳い上げている憲法が、いったいどこの国にあろうか。
このような主権国家の憲法とは言えぬ代物が、どうしてわが国の憲法になったのでしょうか…
それは、この憲法の成り立ちを見れば解ります。
当該憲法が公布されたのは昭和21年11月3日、施行されたのが翌年5月3日です。
戦争が終わり、米国が日本を占領下において1年ちょっとです。
ちなみに、なぜ昭和22年5月3日なのかといえば、その前年の5月3日に、日本にとっては屈辱の「東京裁判」が開廷されたからです。
当時の米国が身に沁みて感じていたのは、勝利したとはいえ戦場で接した日本軍の果敢で勇敢な強さでした。
ゆえに武力に通じるものはすべて叩き潰し骨なしにしてしまうのが、彼らの対日占領政策の主眼だったのです。
日本の強さを徹底的に叩き潰し、元に戻ることができないように骨抜きにしてしまうためには、50年、少なくとも25年はかかると考え、その期間、米国は日本を占領し続けるつもりでいました。
そして、長期間にわたり占領政策を進めるにあたって出てきた基本方針こそが現在憲法です。
要するに現行憲法は、米国様がつくった占領政策基本法だったのです。
そもそも占領下なのですから、主権の発動たる自主憲法を日本が制定することなどできません。
その後の昭和25年、朝鮮戦争が勃発します。
これを機に、戦前戦中の日本の行為が侵略ではなかったことを米国は理解しました。
理解したがゆえに、米国は長期間にわたり日本を占領統治するという方針を急いで転換し、昭和26年にサンフランシスコ平和条約を締結して日本の主権回復を認めたわけです。
このとき、国家主権を回復したわが国は、占領政策基本法である現行憲法を直ちに破棄し、明治憲法に基づいて自主憲法を制定すべきでした。
残念ながら、日本はこの努力を怠ったのです。
よって、法的には次のように解釈すべきです。
占領政策基本法(現行憲法)は、占領国(米国)と非占領国(日本)との間に締結された約束事、すなわち条約(東京条約)です。
ハーグ条約(陸戦の法規慣例に関する規則)第43条(占領地の法律の尊重)では、「占領軍が占領地における権力を事実上獲得した場合、占領者は可能な限り、占領地の現行法を尊重し、公共の秩序と安全を回復・確保するため、必要なあらゆる措置を講じなければならない」と規定されている以上、占領国(米国)が非占領国(日本)の憲法を制定することはできません。
なので、現行憲法は憲法としては無効ですが、明治憲法(第13条)下の講和条約(東京条約)の限度で認められます。
なお、明治憲法第76条第1項にも「法律規則命令又は何等の名称を用いたるに拘らずこの憲法に矛盾せざる現行の法令は総て遵由の効力を有す」ことから、現行憲法は東京条約として有効です。
ちなみに、ポツダム宣言、戦艦ミズーリでの降伏文書の調印もまた、明治憲法第13条の講和大権の発動により受諾しました。
それと同じように、東京条約(占領政策基本法)もまた明治憲法13条の講話大権により締結されたのです。
そもそも現行憲法は、まさに第9条にあるようにわが国に交戦権(講話大権)を認めていません。
認めていないのですから、現行憲法第73条の条約締結権もまた交戦権(講和大権)を有していないのです。
交戦権(講話大権)がないのに、どのようにしてサンフランシスコ講話条約を締結したのか。
むろん明治憲法13条の講話大権に基づいたからです。
よって、わが日本国として成すべきことは、まずは明治憲法の復元改正です。
ここで言う「復元」とは、明治憲法は復元行為によらずとも現存していることの確認、すなわち規範意識を復元することです。
占領統治は明治憲法第8条の緊急勅令によりはじまりましたので、復元改正手続きもまた再び緊急勅令に基づき、その上で占領期の法制度の改変と清算(現行憲法無効宣言など)を行えばいい。
また、講和条約(東京条約)の拘束から逃れるためには、「事情変更の原則」により、米国(連合国)に対して破棄通告をすれば足ります。