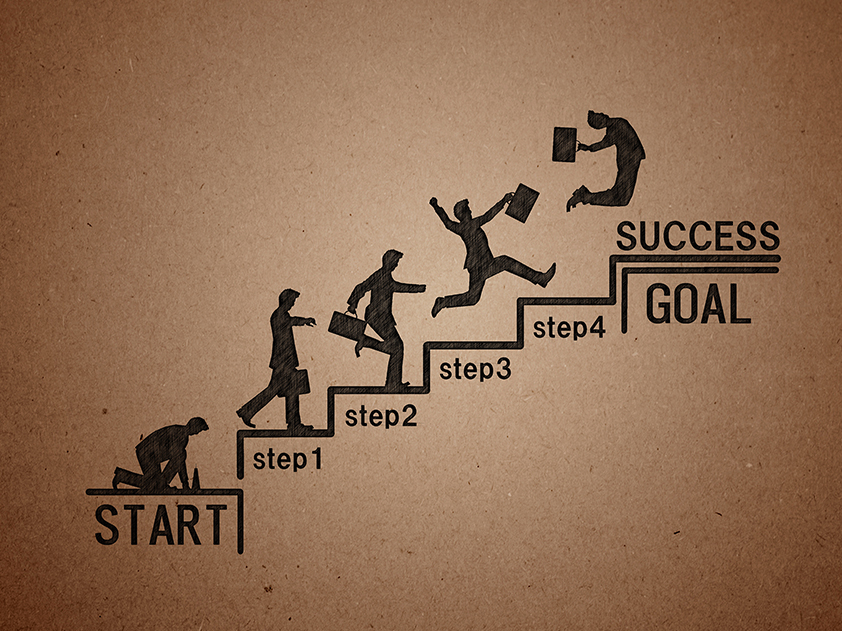日本の食糧自給率の低下に歯止めがかかりません。
その背景には、主因と考えられる減反政策と玄米備蓄(かつては籾米備蓄)があり、さらに農業従事者の高齢化や消費者の食生活の変化、国際貿易の自由化など、複合的な要因が重なっています。
もう一つ、あまり注目されてこなかったのが「財務官僚の出世構造」と農業政策の関係です。
財務省主計局は、予算編成を担う省内の中枢部署です。
その中でも「農林水産担当」は難しい利害調整を伴うため、キャリア上の花形ポストとされています。
とりわけ農業予算は政治的影響が大きく、削減や合理化を図るには高度な調整力が求められます。
このため、この分野で実績を上げることが人事評価に直結すると、官僚OBや政策研究者の間で指摘されてきました。
実際、歴代の財務次官の中には農林水産担当主計官を経験した人物が複数存在します。
具体的な人数については公開データを精査する必要がありますが、農林水産担当が「次官候補コース」の一つであることは広く知られています。
特に農業予算の抑制は、予算編成上きわめて難しいため、成果が評価につながりやすいのです。
この構造が日本の食糧自給率の低下に間接的な影響を及ぼしてきたことは否定できません。
一方、米不足の原因を、インバウンド需要や一時的な買い占めに求める声もあります。
しかし、実際には長年続いた減反政策と玄米備蓄が米の生産量を削減し、供給能力を恒常的に低下させたのです。
農林水産省はようやく増産の方針を打ち出しましたが、財政的な補償が伴わないため、農家はリスクを負ってまで増産に踏み切ることができません。
その背後には、農業予算を削減することで評価を得る財務官僚の人事構造があり、これが農業政策の停滞を招いてきました。
小泉進次郎農相が進めた備蓄米の放出は、災害備蓄の確保よりも政治的配慮、すなわち選挙を意識した施策との批判もあります。
その結果、本来であれば災害や不測の事態に備えるべき備蓄が減少し、食糧安全保障の基盤が弱体化しました。
いま何よりも求められているのは、農家に対する安定的な所得補償や価格補償の制度化です。
そして、政府備蓄も籾米備蓄に戻し、災害や国際情勢の変動に備えられる体制を整える必要があります。
財務官僚の人事構造が農業予算の削減を誘導し、その結果として農業政策が前進できなかった現実を直視すべきです。
我が国の食糧安全保障を守るためには、農業予算の在り方と官僚の出世構造にメスを入れる改革が不可欠です。